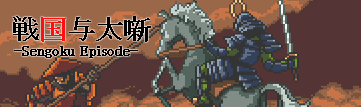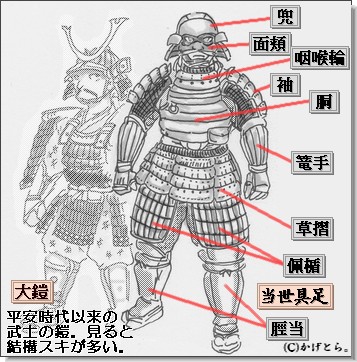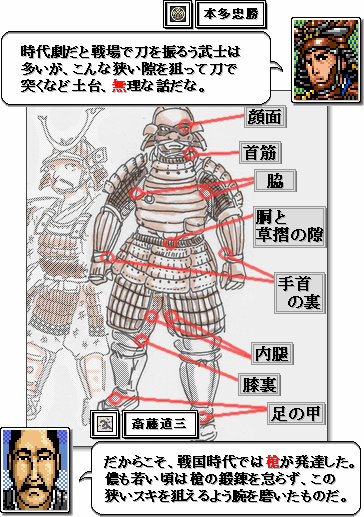さて、日ノ本六十八ヶ国が兵乱の戦渦に巻き込まれた混沌の戦国時代。
今でも日本各地の博物館や歴史資料館、民俗史料館などでは当時の戦国武将が着用していた鎧を見ることが出来ましたが、どれもこれも大変に重厚な出来栄えです。
合戦に臨んだ戦国武将達はどうして、あんな大仰な鎧兜に身を包んだのでしょう。
…――聞くまでもないですよね、そりゃあ『死にたくないから』です。
武士の名誉や正義が重んじられた鎌倉時代なら、戦いは純然とした一騎討ち。
『やぁやぁ、我こそはドコドコの大将の家来で何処其処の国の住人、ナントカカントカなり!! 腕に覚えがある者は掛かってまいれ!!』という名乗りから始まり、その挑戦状に応じる形で敵方からも武者が出る。
そして、邪魔立ていっさいなしのタイマン勝負がはじまります。回りの敵味方は見てるだけ。
『将を射んと欲するなら、まず馬を射よ』だなんて慣用句がありますが、これも重大なルール違反でした。武士は人を弓矢で撃っても馬は撃たないもの、と誇りを持っていたからです。
そもそも、戦闘開始前には『今から始めるぞ!』と果たし状を送るのが当たり前。夜討ち朝駆け、前触れ無しの奇襲なんてもってのほか。
正々堂々とした命のやり取り、正義と名誉が根底にある"決闘"でした。
だからこそ、無様に生き延びるより『いかにして死ぬか』が重要視されたわけですが…そんないさぎよく華々しい合戦の美学・理想的な思想は時代が下るにつれ、徐々に俗物的で現実主義なものに変化していきました。
はやくいえば、戦場に生きる人達のテーマが『どう生き延びるか』に、"決闘"が"サバイバル"に変わっていったのです。
この風潮は戦国時代に入ってから…と思いきや、案外と到来の時代は早く、源平合戦の終わり頃にはもうルールの崩壊が始まっていましたとされています。
『保元の乱』で平清盛が当時の合戦礼儀を破って夜討ちを敢行し崇徳上皇方を敗北させたこと、その平氏が滅んだ壇ノ浦の合戦で源義経が舟戦ではタブーとされていた『舟を漕いでる人を攻撃すること』を遠慮なく行い、舟を動かせなくなった平氏が滅多撃ちにされて滅亡した、などなど…枚挙にいとまがありません。
さぁ…こうなってくると、『いざ尋常に勝負!!』だなんて言ってられません。
死んでしまったらおしまいなんです。奇襲闇討ち騙し撃ち、なんでもありがまかり通る世の中となり、卑怯千万どんと来いという気風になった合戦では、恥や外聞を気にしていては命がいくつあっても生き延びれません。
そんな風潮にしたがい、防具も進化していきます。
『大鎧』と呼ばれていた鎌倉時代以来の鎧兜…
大柄かつ重厚で身動きの取りづらい、見た目ばっかり綺麗で無駄の多い具足は、『敵からの攻撃を合理的に防御・回避が出来、戦場で生き延びやすいように洗練された、隙や無駄がないもの』に変わっていきました。
このような戦国時代向けに進化・調整された鎧兜のことを『当世具足』(とうせいぐそく)と言います。
大河『風林火山』の頃…ちょうど山本勘助が生きた時代は、古い時代の大鎧が新しい時代の当世具足に進化していく過程にあり、その両方ともが戦場に混在している時期でした。
大河『風林火山』でも、武田信虎や北条氏綱など各大名家の最高司令官クラスは赤や緑の飾り糸で編み上げられた昔ながらの大鎧を着用していますが、甘利虎泰や板垣信方といった前線指揮官クラスは黒っぽい鉄製の当世具足を着込んでいるのがわかります。
これは、大将格は実際の"現場"…命のやり取りの最前線に行く必要が無いから、古い慣習に則って大鎧を着ているからなんです。
もう少し時代が下って織田信長や豊臣秀吉の時代になると、大将も当世具足をきらびやかに飾った派手なものを着用するようになっていきます。
当世具足の特徴は、なんでもありの戦国時代の合戦に対応するために『様々な敵の攻撃を想定した、とにかく隙が無いつくりであること』でした。
当たり前ですが、刀なんか考えなしに振り下ろしても、まず致命傷にはならないような頑丈な完全武装です。
兜で頭部を、顔は面頬(めんぽう)できっちり隔し、首筋は錣(しころ)と小鰭(こびれ)という鉄入りの襟で、のど元は咽喉輪(のどわ)が隙間無く覆う。
胴は剣道の防具でもおなじみのあれがあるとして、腰は草摺(くさずり)という鉄板を編んだ楯が釣り下がり、太股には佩楯(はいだて)、脛は脛当(すねあて)。
腕は袖や篭手が大鎧の時代から完全ガードしているから…日本刀を普通に振りかぶって斬りつける、のでは大きなダメージが与えられなかったと考えられます。
…――しかし、それなら戦国武将達はどうやって当世具足で完全武装した敵を倒すことが出来たのでしょうか。
真っ向から斬り倒したんじゃなくて、鎧の隙間を突き倒したり、矢で射抜いたり、殴り倒してたんです。
当世具足でも守りきれない場所や攻撃方法、いわば『鎧兜の急所』を狙ったわけです。
ここまで完全武装しても、目元やこめかみには隙間があるのでそこを切っ先で突く。そして、相手が少しでも襟元を広げたら脇が開きます。脇はがちがちに固めてしまうと腕が動かせないので装甲に隙間があります。そこめがけて、一撃をみまう。
いくら窮屈に防具を詰めても脇や腕の裏側までは鉄板で覆えないので、そこも弱点。
胴と草摺にも隙間がありますので、そこを深くえぐれば内臓に達し一撃必殺となりますし、槍や薙刀などの長い竿状武器にしているなら、太股の内側なども狙い目になります。
そうそう、意外な場所では足の甲も弱点のひとつ。
ここを彼女に踏んづけられてうめき声を上げた覚えがある殿方ならお分かりでしょうけれど、足の甲は神経が集中しているので痛覚に敏感な場所なんです。
槍の柄でここを思いっきり引っ叩くと、さしもの戦国武将も動けなくなったと当時の史書は伝えています。
あと、これは看護婦さんなどの医療従事者の方ならピンとくるかも知れませんが…以上で述べたの急所は全部、動脈が通っている場所ですので、刃物で斬りつけられれば相手は出血多量で意識朦朧となり、とてもじゃありませんが戦える状態ではなくなります。
以上を踏まえれば、幾ら当世具足が頑丈であっても『斬られる』ことは防げても『突き刺される』攻撃は防ぎきれなかったことが判ります。
斎藤道三や本多忠勝、前田利家や前田慶次郎(ぉ?)ら槍の達人が戦国武将に多かったのは、『当時の鎧武者には刀よりも槍が圧倒的に効果が高かった』ことは決して無関係ではありません。
また、当世具足は上位互換である『南蛮胴具足』と違い、装甲という概念ではなく…構成が『小さな鉄や革をつなぎあわせた集合体』であるため、『殴る、叩かれるなどの衝撃』に対しても磐石とは言えなかった様です。
戦国時代の武将には金砕棒や根、巨大な杖などを振り回して戦った者もあると記憶に残されていますが、それは『いくら当世具足でがちがちに固めても、渾身の一撃でぶん殴れば命は取れる』からだということを意味してもいます。
時代劇では鎧武者が真正面からバッサリ斬って捨てるのは飽くまで演出上の話。実際の戦国時代は、この僅かな油断と隙を狙って、お互い血まみれになりながら一撃必殺を突き刺す…スタイリッシュもへったくれもない血生臭い闘いだったわけです。